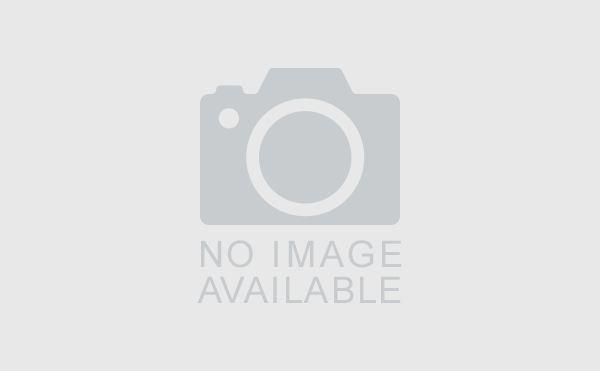家庭でできる!今日から始めるエコ習慣5選
はじめに:環境問題は身近な問題になっている
近年、地球温暖化の影響による異常気象や海面上昇、そして増え続けるプラスチックごみによる海洋汚染など、環境問題は私たちの生活に直接的な影響を与えるようになりました。
気温の上昇により熱中症のリスクが高まり、豪雨や台風の被害も深刻化しています。
また、日々の生活で出るごみの量も増加の一途をたどり、焼却場や埋立地の処理能力を超える状況も各地で起きています。
こうした問題は決して遠い国の出来事ではなく、私たちの日常生活と密接に関わっています。
しかし、環境保護というと
「大変そう」「お金がかかりそう」
というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか?
実は、家庭でできる環境に優しい取り組みは、特別な道具や大きな投資を必要とせず、むしろ家計の節約にもつながるものがたくさんあります。
今回は、今日からでも気軽に始められるエコ習慣を5つご紹介します。
一人ひとりの小さな行動が積み重なって、大きな変化を生み出すことができるのです。
1. マイボトルの活用で使い捨てプラスチックを減らそう
なぜマイボトルが環境に良いのか
日本では年間約230億本のペットボトルが製造されており、そのうちリサイクルされるのは約85%です。
一見高いリサイクル率に見えますが、残りの15%は焼却処分されるか、最悪の場合は自然環境に流出してしまいます。
また、リサイクル過程でもエネルギーを消費するため、そもそもペットボトルを使わないことが最も環境負荷の少ない選択肢なのです。
マイボトル生活を続けるコツ
マイボトルを習慣化するためには、持ち運びやすさと使い勝手の良さが重要です。
軽量で保温・保冷機能のあるステンレス製ボトルを選ぶと、一年中快適に使用できます。
容量は350ml~500ml程度が日常使いには最適でしょう。
また、職場や学校に給湯器や浄水器がある場合は、そちらを活用することで飲み物代の節約にもつながります。コーヒーや紅茶が好きな方は、インスタントタイプを小分けにして持参すれば、いつでも温かい飲み物を楽しめます。
経済的なメリットも大きい
毎日150円のペットボトル飲料を買っている場合、年間で約55,000円の出費になります。
マイボトルなら2,000円~3,000円程度の初期投資で、水道代やお茶代を含めても年間10,000円以下に抑えることが可能です。環境保護をしながら家計も助かる、まさに一石二鳥の習慣です。
2. エコバッグを習慣化して脱・レジ袋依存
レジ袋有料化の背景と効果
2020年7月のレジ袋有料化により、多くの人がエコバッグを使うようになりました。
これにより、日本のレジ袋使用量は約7割減少したという報告もあります。
しかし、まだ完全に習慣化できていない方も多いのではないでしょうか。
エコバッグ選びのポイント
エコバッグを選ぶ際は、以下の点を重視しましょう。
エコバック選びのポイント
- 容量
- 強度
- コンパクトさ
- 選択可能か
まず、強度と容量です。
重い商品を入れても破れない丈夫な素材で、普段の買い物量に対応できるサイズを選びます。
次に、コンパクトに畳めることです。
小さく畳めてカバンに常備できるタイプなら、急な買い物でも忘れる心配がありません。
また、洗濯可能な素材を選ぶことも大切です。
肉や魚のパックから汁が漏れることもあるため、清潔に保てるエコバッグが理想的です。
エコバッグを忘れない工夫
エコバッグを習慣化する最大のコツは「忘れない仕組み」を作ることです。
普段使うカバンやリュックに常に1つ入れておく、玄関に買い物用のエコバッグを置く、車を使う方はトランクに数枚ストックしておくなど、複数の場所に配置しておくと安心です。
スマートフォンの買い物リストアプリに「エコバッグ」を必須項目として登録するのも効果的です。
買い物前のチェックで自然と思い出せるようになります。
3.節水・節電の工夫で地球にも家計にも優しく
水の使い方を見直そう
日本の家庭における水の使用量で最も多いのは以下の順です。
日本の家庭における水の使用量ランキング
- 風呂(40%)
- トイレ(21%)
- 炊事(18%)
- 洗濯(15%)
これらの場面で少しずつ節水を心がけるだけで、大幅な水の節約が可能になります。
シャワー時間を1分短縮するだけで、年間約2,000円の水道代と約4,000円のガス代を節約できます。
髪を濡らす時とすすぎの時以外はシャワーを止める、体を洗っている間は止めるという習慣をつけましょう。
また、節水シャワーヘッドに交換すれば、水圧を保ちながら30%程度の節水が可能です。
待機電力をカットして電気代を削減
家電製品の待機電力は、家庭の電力消費量の約5%を占めています。
年間の電気代に換算すると3,000円~4,000円程度になる計算です。
テレビやパソコン、オーディオ機器などは、使用していない時はコンセントから抜くか、スイッチ付きタップを活用してこまめに電源を切りましょう。
エアコンの設定温度を夏は1度上げ、冬は1度下げるだけで、約10%の電力消費削減につながります。
また、フィルターの掃除を月1回行うことで、エアコンの効率が向上し、さらなる節電効果が期待できます。
冷蔵庫の使い方を改善
冷蔵庫は24時間稼働する家電のため、使い方を改善するだけで大きな節電効果があります。
冷蔵庫の詰め込みすぎは冷気の循環を悪くし、余計な電力を消費します。
逆に冷凍庫は適度に食品が入っている方が、お互いが保冷剤の役割を果たして効率的です。
また、冷蔵庫の開閉回数を減らし、開けている時間を短くすることも重要です。
何を取り出すか決めてから開ける習慣をつけましょう。
4. リユースアイテムで使い捨て文化から卒業
蜜蝋ラップで食品保存革命
蜜蝋ラップは、天然の蜜蝋とコットン生地で作られた再利用可能な食品ラップです。
従来のプラスチックラップと違い、洗って何度でも使えるため、プラスチックごみの削減に大きく貢献します。
手の温度で柔らかくなり、容器や食品にぴったりと密着する特性があります。
使い方は簡単で、おにぎりやサンドイッチを包んだり、ボウルの蓋として使ったり、カットした野菜や果物の保存に活用できます。
冷水で洗って自然乾燥させるだけでお手入れも簡単です。
適切に使用すれば1年程度は使用できるため、コストパフォーマンスも優秀です。
その他のリユースアイテム
蜜蝋ラップ以外にも、日常生活で活用できるリユースアイテムはたくさんあります。
シリコン製の食品保存袋は冷凍・冷蔵・電子レンジ・食器洗浄機に対応しており、使い捨ての冷凍用袋の代替として活用できます。
マイ箸やマイスプーンを持参すれば、コンビニ弁当や外食時の使い捨てカトラリーを削減できます。
木製や竹製のものは軽くて持ち運びやすく、専用のケースも販売されているため携帯に便利です。
また、古いTシャツやタオルを小さく切って掃除用のウエスとして再利用すれば、使い捨てのお掃除シートの使用量も減らせます。
新品の衣類ではなく古着利用することで、1kg当たり(コットンTシャツ4枚程度)10kgほどのCO2が削減できると発表されています。
5. フードロスを減らす冷蔵庫整理術
日本のフードロス問題
日本では年間約600万トンの食品ロスが発生しており、その約半分の280万トンが家庭から出ています。
これは日本人一人当たり年間約51kgの食品を捨てていることになり、金額に換算すると一世帯あたり年間約6万円分の食品を無駄にしている計算です。
冷蔵庫の「見える化」で食品ロスを防ぐ
フードロスを減らすための第一歩は、冷蔵庫の中身を把握することです。
冷蔵庫の扉に在庫リストを貼ったり、スマートフォンで中身を写真撮影して買い物前にチェックしたりする方法が効果的です。
また、「手前から使う」ルールを徹底しましょう。
新しく買った食品は奥に、古いものは手前に配置して、賞味期限の近いものから使い切る習慣をつけます。
透明な保存容器を使うことで、中身が一目で分かるようになり、存在を忘れることも防げます。
近年では、冷蔵庫を開けなくても中身が把握できるような冷蔵庫も販売されています。
▼ツインバード中身が見える冷蔵庫
▼HITACHI見えるカメラ搭載冷蔵庫
賞味期限と消費期限の違いを理解
多くの人が混同しがちなのが「賞味期限」と「消費期限」の違いです。
賞味期限は「おいしく食べられる期間」を示しており、多少過ぎても食べることができます。
一方、消費期限は「安全に食べられる期間」のため、こちらは守る必要があります。
賞味期限が近づいた食品は、冷凍保存や調理方法を工夫して使い切りましょう。
野菜は傷みやすい部分を除いて炒めものやスープに、肉類は冷凍保存で期限を延ばすことができます。
計画的な買い物で無駄をなくす
フードロス削減には、計画的な買い物が欠かせません。
1週間分の献立を大まかに決めてから買い物に行く、冷蔵庫の在庫をチェックしてから出かける、空腹時の買い物は避けるなどの工夫で、必要以上の食品購入を防げます。
また、まとめ買いは節約になりますが、一人暮らしや少人数世帯では食べきれずに無駄になることも多いため、適正な量を見極めることが大切です。
まとめ:今日からできる一歩を始めてみよう
環境保護というと大げさに聞こえるかもしれませんが、今回ご紹介した5つの習慣は、どれも特別な準備や大きな投資を必要としないものばかりです。
マイボトルやエコバッグの活用、節水・節電の工夫、リユースアイテムの導入、フードロス削減の冷蔵庫整理術は、環境に優しいだけでなく、家計の節約にもつながる一石二鳥の取り組みです。
重要なのは、完璧を目指さず、できることから少しずつ始めることです。
最初は1つの習慣から始めて、慣れてきたら他の習慣も取り入れていけばよいのです。
例えば、今週はマイボトルを持参することを意識し、来週はエコバッグを忘れずに持参するといったように、段階的に習慣化していきましょう。
一人ひとりの小さな行動が集まれば、社会全体に大きな変化をもたらすことができます。
未来の世代により良い地球環境を残すために、今日からできる一歩を踏み出してみませんか。
あなたの行動が、きっと地球と家計の両方を救ってくれるはずです。